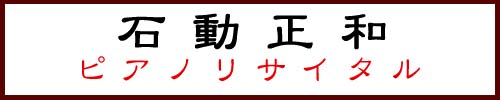
京都コンサートホール(小ホール)
1998 年 12 月 23 日(水・祝)15:00 〜
以下は、上記演奏会プログラムよりの抜粋です。
| 「 遠 く を 聞 く 」 |
|---|
|
この演奏はよく分かる、しかしあの演奏はよく分からないという違いが生じるのはなぜでしょうか。音楽が分かるためには「遠くを聞く」ことが必要です。遠くを聞くとは、一見混沌とした音の中に同じフレーズを見い出すことです。 同じフレーズは、時間軸上様々な周期で現れます。例えばソナタ形式における主題提示部と再現部は長い周期で、ロンド形式(ABACADA)のAは中位の周期で、動力学的手法におけるモティーフは短い周期で生じる例です。時には全く同じ繰り返しではなく変化することがあります。例えば変奏形式では、同じフレーズに様々な変化を与えて曲を展開していきます。このように同じフレーズが繰り返された時、その再現を感知するのが遠くを聞く力です。そして構成の理解のうえに表現の統一がなされた時、その演奏はよく分かる演奏になります。私は同じフレーズを繰り返す場合、一回目は少し強めに弾き、二回目にはソフトペダルを用いて音を弱め音色を変化させることがあります。これは、聞く側に潜在する遠くを聞く力を呼び覚ますことをねらっているのです。 ところで解析学では、こうした繰り返しの程度を「自己相関性」と呼びます。自己相関性の高い音楽は、構成は明確だが時には理屈っぽい印象を与えます。強制的に近くを聞かされてしまうからです。ベートーベンの音楽を解析すると、多くの作品で自己相関性が幾分高いことが知られています。一方逆に、この自己相関性が低い場合には、自由な印象を与えますが、行き過ぎると不安感を催させることが知られています。遠くを聞くにも遠すぎて自己相関性を感じ取れないからです。即興性がポイントになるジャズは自己相関性がやや低い代表です。しかしそれでも和声進行に限れば厳密に自己相関性が保たれています。さて、行き過ぎもなく足り無くもない適切な自己相関性が認められる代表例は何でしょうか? それはモーッアルトだそうです。永遠に愛される音楽には、それだけの必然性があるのです。 |
| イ ン タ ビ ュ ー | |
|---|---|
| Q: |
最近二〜三ヶ月ごとにリサイタルを開かれていますが、なぜ仕事と演奏活動が両立するのですか? |
| A: |
確かに高校・大学の先輩の中には、心配して声をかけてくる人もいます。仕事の方は大丈夫なのかと言うのです。幸い今回、職場からもたくさん来られるので、仕事ぶりについては明確に証言してくれることでしょう。ところで、私の手のひらの生命線は二本あって平行線を描いています。この多重生命線のお陰で、まあ両立できているのかも知れません。 |
| Q: |
それでは演奏活動で一番苦労されていることは何ですか? |
| A: |
演奏自体もさることながら、多くの方に来て頂くための「お知らせ」が実は一番大変です。一般的には、会場定員の数〜十倍の案内が必要と言われています。例えば今回の場合、案内数は実に5,000です。私の場合、職場、大学・中高校の同窓会、音楽団体、ご近所、郷里、親族など複数の場があり比較的恵まれていますが、多くの演奏家はいずれも大変苦労していると思います。 |
| Q: |
暗譜はスムースに行きますか? 暗譜が公開演奏への大きな壁になっている人もいます。 |
| A: |
私にとっても同じでした。以前は暗譜できたら人前で弾けると思っていましたが、結局いつまで経っても出来ません。ある研究者が、実現できるかどうか分からないが何としても達成したい研究目標については、まず公言しその後必死で取り組むと言っているのを思い出しました。実現できなければ恥なので、自らプレッシャーを懸けて頑張ると言うのです。これにヒントを得て、私は演奏会については、あるレベルに来たと思ったら早めに案内を出してしまいます。同じく退路を断つ訳ですが、集中力は相当変わってくるように思います。 |
| Q: |
あなたは昨年燕尾服を買われました。これも退路を経つことになったのではありませんか? |
| A: |
そう思います。スーツ程安くはないので、出来るだけ続けようと決心しました。ところで最初に燕尾服を着たのは柏市の「千葉県民プラザ」でしたが、服が出来たのがその前日、ステージに出る直前に初めて着たのですが、吊りズボンのサスペンダーをロックするのを忘れていたのです。ピアノはベーゼンドルファーで素晴らしい響きでした。夢中で弾いていると段々ズボンが下にずり落ちてきます。演奏が終わりステージを去る時はまるでチャップリンの様でしたね。客席で気付いた人もいて大笑いです。しかしあの時のピアノは最高でしたね。 |
| Q: |
今回のプログラムについてコメントを頂けますか? |
| A: |
私はこれまで自分本位のプログラムで演奏を続けていましたが、その後多くの方から「もっとポピュラーな曲を」と言われるようになりました。自分が追求している世界をアピールすることと多くの方に楽しんでもらうことの同時実現が理想ですが、やはり曲によっては明らかに異なるものがあります。今回は、プログラムの前半と後半で大きく変化を付けています。前半は比較的よく知られた曲を中心に、後半は全てスクリャビンです。私はこの作曲家を暫く追いかけるつもりです。 |
|
(インタビュアー)ラ・プリマベーラ: 村林 成 |
|
ホームへ戻る