第4回演奏家に向かってバッハのミサ曲ロ短調を取り上げている間は、浅学を省みずほぼ毎月20回にわたってバッハやミサ曲ロ短調に関する資料を配布させてもらいましたが、今回もヘンデルの「メサイア」を取り上げるにあたって、何かのお役に立てればと思い、性懲りもなく、私なりに書いてみることにしました。
何分バッハに比べるとヘンデルに関しては、公刊されている資料がほとんどなく、「メサイア」についても「ミサ曲ロ短調」のように議論を呼ぶような謎もないので、前回のように毎月書く材料はないと思います。その一方で「メサイア」はわが国でもかなり前から広く演奏されていたことから、関連の資料から入手できる程度の情報はインターネットで入手できるので、何をどう書けば良いか考えが良くまとまっていませんがとにかく書けるところから書いてみることとしました。
なお、「メサイア」そのものについては、インターネットの情報のほかに、「メサイアハンドブック」(三ヶ尻 正著、ショパン出版)という実用的な観点から非常にうまく整理された本が出ているので、是非参考にされることをお勧めします。
今回は第1回として、ヘンデルの生涯を簡単に紹介して、ヘンデルへの親近感を少しでも持っていただけたらと思います。今後ともバッハとの比較で論じることが多くなると思いますが、今回取り上げた生涯という点から二人を比較すると、生まれた年は同じで、生まれた場所もドイツ中部という点で共通点はあるものの、生涯は対照的で、バッハが幾度か転居したもののドイツ中部を離れなかったのに対し、ヘンデルは早くから当時の音楽の最先進地域であったイタリアで活躍し、途中からイギリスに渡って生涯の大部分をその地で活躍しました。従って、ヘンデルは当然、ドイツ語の他に、イタリア語、英語、さらにはフランス語も話したといわれていますが、バッハの場合はドイツ語以外の言語を話せたと類推される事実は残っていません。
音楽活動を、誤解を恐れず包括的に言えば、バッハが教会での活動が中心で、いわば神に聞かせるために音楽を書いたのに対し、ヘンデルは若いときはオペラに、ある時期からはオラトリオを中心に活躍しますが、いずれも劇場で一般大衆を対象として、いわばエンターテインメント作曲家であったといえます。また、バッハは生前は演奏家としての評価は高かったものの作曲家として高い評価を受けるのは19世紀に入ってからであったのに対し、ヘンデルは生前から作曲家として高い評価を受けていたのも対照的です。
私生活も対照的で、バッハが2度結婚し、合計20人の子供をもうけたのに対し、ヘンデルは生涯独身を通しました。ただ、最後だけが面白い共通点があって、白内障を治す名医という触れ込みにだまされて同じ医者から白内障の手術を受け、それがもとで体調を崩して、術後まもなくなくなっています。
前置きが長くなりましたが、以下にヘンデルの生涯を概説します。
1.生い立ち
ヘンデルは1685年2月23日、ドイツ中部のハレで生まれました。この年はヨハン・セバスチャン・バッハが生まれた年でもあり、ハレという町は、バッハが生まれたアイゼナッハからは直線で130kmほど、後半生を送ったライプツィッヒの西35キロメートル位のところに位置します。
バッハが音楽一家に生まれたのに対し、ヘンデルの家系は音楽とほとんど関係がなく、父親ゲオルクは宮廷つきの医師、祖父ヴァレンティンは銅細工師でした。このため、ヘンデルが音楽の道を志したときに父親は反対しましたが、ヘンデルはそれを押し切って音楽の道を選びます。
ハレという町は、ヘンデルが生まれる少し前からブランデンブルグ辺境伯クリスティアン・ヴィルヘルム(1587〜1665)の宮廷が置かれ、ドイツの初期バロックを代表する作曲家の一人ザムエル・シャイト(1587〜1654)や、ミヒャエル・プレトリウス(1571または1572〜1621)が活躍しました。その後、戦乱などの混乱期を経て、1638年には平和が訪れましたが、ヘンデルが生まれるころには宮廷がヴァイセンフェルスに移ったため、宮廷楽団もハレを離れました。
その後は教会を中心とした音楽活動が行われ、ヘンデルはマリア教会のオルガニスト、フリードリッヒ・ヴィルヘルム・ツァハウ(1663〜1712)に音楽教育をうけ、改革教会のオルガニストして活躍しました。
2.ハンブルグからイタリアへ
1703年、17歳の時にハンブルグオペラのヴァイオリン奏者となり、後に通奏低音奏者になりました。作曲活動も進め、1705年に最初のオペラ〈アルミラ〉を作曲して成功を収めました。しかし、ハンブルグオペラそのものが堕落の兆候を見せ始めたために見切りをつけ、1706年に当時音楽の最先進地域であったイタリアに向かいます。
ローマ、ヴェネツィア、ナポリなどを回って、スカルラッティ親子、コレルリ等のイタリア楽壇の大御所と知り合い、優れたオルガン奏者、チェンバロ奏者として歓迎されました。また、引き続いて〈ロドリゴ〉、〈アグリッピーナ〉等のイタリアオペラの作曲も行い、いずれもイタリア人から喝采を浴びました。
3.ハノーファーからロンドンへ
1710年、ヘンデルは、イタリア音楽家アゴスティーノ・ステッファニ(1654〜1728)の推薦によって、ハノーファーの宮廷楽長に就任しました。ハノーファーは16世紀以来音楽が盛んな町で、16世紀はルター派の教会音楽が中心になっていましたが、1636年にカーレンベルク公国の宮廷が置かれてから、宮廷に活動の中心が移っていきました。
領主の改宗など色々な情勢の変化の度にフランス風の音楽が支配的になったり、イタリア風の音楽が支配的になったり流動的でしたが、1670年ごろからイタリア音楽が主流になりオペラ劇場も建てられる状況にありました。1688年から1695年まで宮廷楽長を勤めていたのが、前述のステッファニでした。
ヘンデルはイタリア音楽の能力を買われて推薦されたと推定されますが、彼は就任後直ぐに休暇をとって、母親のいるハレの町を訪ねた後、デュッセルドルフ、オランダを回ってロンドンにやってきました。当時、ロンドンではすでにイタリアオペラの上演が盛んに行われており、ヘンデルも1711年にロンドンで最初のオペラ〈リナルド〉を上演し、予想以上の成功を収めました。
この年の6月、一旦ハノーファーに戻りますが、その地ではほとんど足跡を残さないまま、1712年秋、再びロンドンに渡り、そのまま生涯を過ごします。一方、ハノーファーの方は、1713年に新しい宮廷楽長を任命することになりました。
4.オペラ作曲家時代
1712年秋に戻ってから、オペラ作曲活動を再開し、〈忠実な羊飼い〉等を次々に作曲していきました。興行的には常に大成功というわけには行きませんでしたし、時には劇場経営者が資金を持ち逃げして上演不能の危機を味わったこともありましたが、平均的には成功といえる状態で、クィーンズ劇場を中心に、ロンドンのイタリア・オペラを盛り上げていきました。
この時期はオペラ作曲とともに、貴族の館での音楽活動なども盛んに行い、それをみた宮廷が祝祭用の音楽の作曲を依頼することもありました。ちょうどこの時期スペイン継承戦争がようやく収まる見通しが出てきたため、そのための音楽や王女の誕生日のための祝祭音楽などが作曲されました。
1714年に運命のいたずらのようなことが起こりました。アン王女が急死したため、ハノーファー選帝侯ゲオルグ・ルードヴィッヒがイギリス王ジョージ1世となったのです。つまり、折角宮廷楽長に任命されたのに、禄にお仕えもせずに放り出してきた元の雇い主が追いかけてきたようなことになったわけです。わが国でもヘンデルの作品として最も名高い曲の一つである「水上の音楽」が作曲されたのがちょうどこの時期ですので、気まずい思いをしたヘンデルが密かに作曲演奏して、ジョージ1世の許しを得たという説がかつて信じられていたのですが、今日では単なる面白いお話に過ぎないというのが定説になっています。なお、ジョージ1世はハノーファーにいることの方が多く、音楽にもあまり熱心ではなかったようです。
王様が代わった後もヘンデルは従来と同じようにオペラや宮廷の祝祭音楽、また、イギリス独特の音楽劇ともいえる“マスク”の音楽などの作曲を続けます。記録に残っている話題としては、1719年にドレスデンへロンドンのための新しい歌手探しに行き、何人かお目当ての歌手を引き抜くことに成功し、反対に引き抜かれたドレスデンのオペラ界は大混乱に陥り、閉鎖する劇場もあらわれました。また、この時、かねてヘンデルのうわさを耳にしていたバッハが一度会いたいと思い立ってハレまで出かけていきますが、少しのところで行き違いになりついにこの二人が出会うことはありませんでした。
5.イギリス帰化
既にイギリスで長く活躍していますが、それでもヘンデルは、ゲオルク・フリードリッヒ・ヘンデル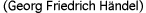 というドイツ人でした。それが何がきっかけになったのか明記した資料はありませんが、1724年にイギリスに帰化し、名前もジョージ・フリデリック・ハンデル(George Freideric Handel)と改名しました。わが国ではドイツ語読みで通用していますが、本人は「それ誰のこと」と言っているのかも分かりません。私自身、アメリカでラジオを聴いていて「ハンデル作曲の‥‥」というアナウンスを聞いて誰のことかと思っていたら流れてきた音楽がヘンデルの曲だったので、英語圏の人間はこう発音するのかと納得した覚えがあります。 というドイツ人でした。それが何がきっかけになったのか明記した資料はありませんが、1724年にイギリスに帰化し、名前もジョージ・フリデリック・ハンデル(George Freideric Handel)と改名しました。わが国ではドイツ語読みで通用していますが、本人は「それ誰のこと」と言っているのかも分かりません。私自身、アメリカでラジオを聴いていて「ハンデル作曲の‥‥」というアナウンスを聞いて誰のことかと思っていたら流れてきた音楽がヘンデルの曲だったので、英語圏の人間はこう発音するのかと納得した覚えがあります。
6.オペラ作曲家としての後半
イギリスに帰化した直後1727年2月13日に正式に王室礼拝堂付作曲家および宮廷作曲家に任命されますが、これはいわば名誉職のようなもので、以前と変わりなく次々とオペラを作曲していきます。しかし、1720年代に入るとジョバンニ・ボノンチーニ(1670〜1747)というヘンデルに対抗する勢力も現れ、ロンドンのオペラ界全体がヘンデル派とボンチーニ派に分かれて何かにつけ対立するようになります。また、有力な歌手同士がいがみ合うというような事態も多発したといわれていますが、そのような時期に、ヘンデルが活動の中心としていた王立アカデミーの行き方を批判する、英語でしかもなじみ深い旋律を取り入れた《乞食オペラ》といわれる新しい動きも起こってきます。こういう状況の変化を受けて、1728年には王立音楽アカデミーの倒産という事態も発生します。
王立音楽アカデミーは直ぐに活動を再開し、5年間の予定で引き続いてキングズ劇場でオペラ公演を続けることとし、ヘンデルも倒産前と同様、オペラ作曲家として活躍します。ところがこの5年間の後半になると、ヘンデルのやり方に批判が強まり、アカデミーで歌っていたメンバーの相当数が、皇太子の支援を受けて、別のオペラ公演組織を結成してしまいます。ヘンデルは、予定の5年間が1734年に終わっても暫くオペラでの活動を続けます。活動の場は1734年からはコヴェント・ガーデン劇場に代わりました。
別組織は1737年まで活動しましたが、皇太子の熱が冷めたことなどからその年で解散し、ヘンデルが再び、キングズ劇場に戻り、1738年までオペラの作曲を続けます。
また、この期間、王室からの注文で祝祭音楽を書くことも続いており、《ジョージ2世のための戴冠式アンセム》、《アン王女のための結婚アンセム》などが残されています。
7.オラトリオ作曲家への転向
前述のようにオペラの作曲、公演活動は続けるのですが、横暴な歌手との軋轢、帰化したといっても出生が外国人であるヘンデルに対するイギリス人の反発、加えて1738年の再度の経済的破綻等の苦労が続き、次第にオペラに対する情熱は冷めたようです。
オラトリオは舞台装置、衣装を伴わない音楽劇ともいえるものですが、ヘンデルはオペラに活躍している間にも時折オラトリオを作曲しており、記録に残っているものでは1708年に最初に作曲しています。
1736年から数年間はオペラとオラトリオの並存期で、今でも比較的知られているものとして、1736年にオラトリオ《アレキサンダーの饗宴》1738年にオペラ《セルセ》(冒頭のアリア「オンブラ・マイ・フ」が有名)などがありますが、オペラは1741年の作品が最後でその後はオラトリオだけになって行きます。結局、終生で作曲したオペラの数は36曲といわれています。
オラトリオは旧約聖書を題材にしたものが殆どで、演奏は教会での礼拝を意識したものではなく、劇場での公開演奏会での演奏を前提にしたものです。
現在残っている記録では、1740年ごろから、毎年1〜2曲のオラトリオが作曲され、1741年に現在われわれが取り組んでいる《メサイア》が完成しました。ただ、《メサイア》だけはその題材のためか、有料の公開演奏会で演奏されずに、慈善演奏会で演奏される機会が殆どでした。《メサイア》以外のオラトリオが日本で演奏する機会は殆どありませんが、その中で唯一、曲中の合唱曲1曲が盛んに演奏されている曲があります。「勇士は帰りぬ」という名前で、表彰式での定番となっている曲がそれで、もともとは《ユダス・マカベウス》という1747年に作曲されたオラトリオの1曲です。
オラトリオ作曲家となってからも、宮廷の祝祭音楽の作曲は続きます。声楽曲も幾つかありますがなんといっても有名なのは《王宮の花火の音楽》でしょう。これはオーストリア継承戦争が1748年にようやく終結し、その祝典が1749年に開かれたときのために作曲されたものです。
1751年になって視力が急に減退し、1752年には視力を失いました。バッハと同じ眼科医の手術を受けますがバッハと同様その効果はありませんでした。手術を受けた時期は今手元にある資料でははっきりしませんが、手術が裏目に出て視力を完全に失ったのか、視力を失ってから回復を目論んでやはりだめだったのかは不明です。
視力を失ってからは旧作の再演や、即興演奏で音楽活動を続けていましたが、1759年4月14日(復活祭の翌日)に死亡し、ウェストミンスター寺院に埋葬されました。
以上、オペラ、オラトリオを中心にヘンデルの生涯を簡単に紹介しましたが、当然ながら、これ以外にも各種の器楽曲、カンタータや独唱曲といった声楽曲も作曲しました。数の点ではバッハに劣らないともいわれていますので、どのような曲を書いたかについては回を改めてご紹介したいと思います。
8.アーノンクールの概説
前項までに一通りの生涯を紹介しましたが、現在バロック音楽で最も活躍している指揮者の一人である、ニコラウス・アーノンクールが著書「古楽とは何か」のなかで、簡潔にヘンデルの生涯を紹介していますので、最後にこれを引用しておきたいと思います。私の下手な文章より、これを読んでいただいた方がイメージがわきやすいかも分かりません。
ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルは彼の時代における最初の俸大な世界人であった。ヘンデルはすでに経歴の開始において作曲家として、魅力的なオルガンの名手として、即興演奏家として成功を収めた。彼の作品は常に特定の機会、特定の会場、特定の聴衆を前提として書かれた。彼が大成功した大きな理由は、彼がその時々の聴衆が理解できる音塞言語を用いて音楽を書いたことである。言い換えれば、彼は達者な演説家のように聴衆のレベルに合わせたのだった。ヘンデルの作品は作曲家と聴衆の問の交流を映し出した鏡像であり、彼自身、芸術家の道徳的課題-彼の音楽を聴くことによってより善なる人間となる-を完全に意識していた。
ヘンデルは当時の音楽のあらゆるスタイルを根本から学んだ。18歳にしてハンブルクのオペラでヴァイオリニスト兼チェンバリスト兼作曲家として働き、22歳のときに当時間違いなくバロック時代の音楽生活の中心であったイタリアに旅し、熱心な芸術保護者オットボー二枢機卿のサークルに出入りするようになった。同地でヘンデルはコレルリ、スカルラッティといったイタリアの最重要作曲家とともに仕事をし、彼らの書法を学んだ。こうして彼は何でもやりこなせる技能を獲得し、自作をみずから演奏できる正真正銘の音楽家となった。彼の教養、外国語のうまさ、あらゆる芸術への関心(ヘンデルは後にイギリスで絵画を収集したが、それは重要なコレクションとなった)が、聴衆の要望に正確に応えるという生まれながらの器用さにさらに磨きをかけた。すでにハンブルク時代から、ヘンデルは世界的(ヨーロッパ的)規模で作品が流通する著名作曲家に数えられていた。1706年から1710年までイタリアに滞在して成功を収めたのちは、ドイツの複数の宮廷が新しいスターをつなぎとめようと文字どおり彼に殺到するようになったが、ヘンデルは自分の価値を意識的に利用した。彼は、古典派時代以前に社会的にも経済的にも成功を収めた数少ない作曲家の一人だった。出版社との共同作業が彼の作品を大いに流通させ、確実な報酬を約束したのは間違いない。それゆえ、ヘンデルの作品の大部分が同時代のさまざまな出版社から発行されたのは不思議ではなかった。そのなかには、版が違ったり、楽器法が異なっているものがいくつかある。
(Bass 百々 隆)
【参考文献】
- バロックの社会と音楽(下) 今谷和徳著、1988年、(株)音楽の友社
- バロック音楽 皆川達夫、1972年、講談社現代新書
- 誰も言わなかった「大演奏家バッハ」鑑賞法、2000年、(株)講談社
- クラシック音楽作品名辞典 井上和男編著、1981年、(株)三省堂
- 古楽とは何か ニコラウス・アーノンクール著、1997年、(株)音楽の友社
|